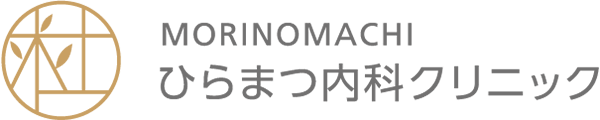秋が深まり、これから年末にかけて飲み会や宴会の機会が増えてきます。
「つい飲みすぎてしまった」「気づいたら体調が悪くなった」といった相談が、外来でも少なくありません。
特に注意が必要なのが、急激に大量のアルコールを摂取したときに起こる急性アルコール中毒です。
命に関わる危険もあるため、適量や予防のポイントを知っておくことが大切です。
そこで今回は、アルコールの性質や適量の目安、急性アルコール中毒を防ぐための方法、そして飲みすぎてしまったときの対処法について解説します。
アルコールの性質と適量の目安

アルコールは消毒薬として使われるように、本来「毒」としての性質を持っています。
体内に入ると神経の伝達が鈍くなり、いわゆる「酔った状態」となります。
さらに分解の過程で肝臓に大きな負担がかかるため、体にとっては有害物質であることを忘れてはいけません。
ただし、適量であれば血管を広げて血流を促進するなど、一時的にプラスの作用をもたらすこともあります。
問題は「適量」を超えた飲酒です。
一般的に適量とされる飲酒量の目安は、缶ビール1本(350ml)、日本酒1合、缶チューハイ1本(350ml)、ワイングラス1杯程度、ウイスキーならショット1杯と言われています。
500ml缶や2杯以上の飲酒は、過剰になると考えてください。
特に女性は男性よりもアルコール代謝が弱く、同じ量でも血中アルコール濃度が高くなりやすいことが知られています。
体格や体質による差もあるため、缶ビール1本でも「飲みすぎ」になる人もたくさんいます。
自分にとっての適量を見極めることが大切です。
急性アルコール中毒を防ぐために

大酒・寝酒を避ける
アルコールは睡眠の質を低下させることが知られています。
寝酒をすると一見眠りやすいように感じますが、眠りが浅くなり、夜中に目が覚めたり翌朝に強いだるさを感じたりします。
二日酔いで「ぐっすり眠れた」という人がいないのはそのためです。
飲み過ぎや寝酒の習慣は、急性アルコール中毒だけでなく慢性的な体調不良にもつながります。
飲酒のタイミングと分解時間
アルコールの分解速度は人によって大きく異なります。
厚生労働省が公開している「アルコールウォッチ」などのツールを使うと、種類ごとに適量や分解時間の目安を知ることができます。
ビールや日本酒、ワイン、蒸留酒ではアルコール度数や分解時間が大きく違うため、運転や仕事に支障が出ないように注意が必要です。
飲酒後に「もう抜けただろう」と思っても、体内にアルコールが残っているケースは少なくありません。
翌朝の運転で検問に引っかかる「飲酒運転の落とし穴」もここにあります。
飲みすぎたときの対処法
飲みすぎてしまったときは、水分補給を最優先にしましょう。
アルコールには利尿作用があり、体内の水分やミネラルが急速に失われます。放置すると脱水症状や頭痛、倦怠感が悪化します。
おすすめは電解質を含む飲み物や味噌汁です。
味噌汁は体を温めながらナトリウムやカリウムを補給でき、失われた水分・ミネラルの回復に役立ちます。
単なる「酔い覚まし」ではなく、体のバランスを取り戻すためのケアだと考えてください。
健康的にお酒と付き合うために

飲めない人に無理をさせない
急性アルコール中毒は、新歓コンパや忘年会、年末年始の集まりなど「一気飲み」の場で起こりやすくなります。
飲めない人やお酒に弱い人に無理に飲ませることは絶対に避けるべきです。
周囲も「飲めない人もいる」という前提を忘れずに、安心して過ごせる環境をつくることが大切です。
自分の適量を知る
普段あまりお酒を飲まない人や初めて飲む人は、缶ビール1本、日本酒1合程度を目安にしましょう。
「少しふらついた」と感じた時点で、それ以上は控えることが必要です。
限界を超えると一気に体調を崩し、急性アルコール中毒に至る危険があります。
休肝日の大切さ
アルコールは肝臓で分解されますが、毎日の飲酒は肝臓を疲弊させます。
肝臓には再生能力があるものの、回復には時間が必要です。
週に1〜2日の休肝日を設けることで肝臓を休ませ、長期的な健康を守ることができます。
「少量だから大丈夫」と思わず、飲まない日を積極的につくる習慣を持つことが肝臓を守る第一歩です。
🍶 🍺 🍷 🍶 🍺 🍷 🍶 🍺 🍷
アルコールは本来「毒」であり、体に大きな負担をかけるものです。
適量を守れば楽しめますが、飲みすぎは急性アルコール中毒や肝障害を引き起こします。
急性アルコール中毒を防ぐためには、適量を意識すること、飲めない人に無理をさせないこと、そして休肝日を設けて肝臓を休ませることが重要です。
これから涼しい季節になり、年末にかけて飲酒の機会が増えてきます。
楽しい時間を安心して過ごすためにも、体をいたわりながらお酒と付き合っていきましょう。
ーー*--*--*--*
ひらまつ内科クリニックは岡山市北区で
呼吸器内科の診療を行っています。
頼れる地域の「かかりつけ医」として、
「困った時の気軽な相談窓口」として、
皆さまの健康に貢献してまいります。